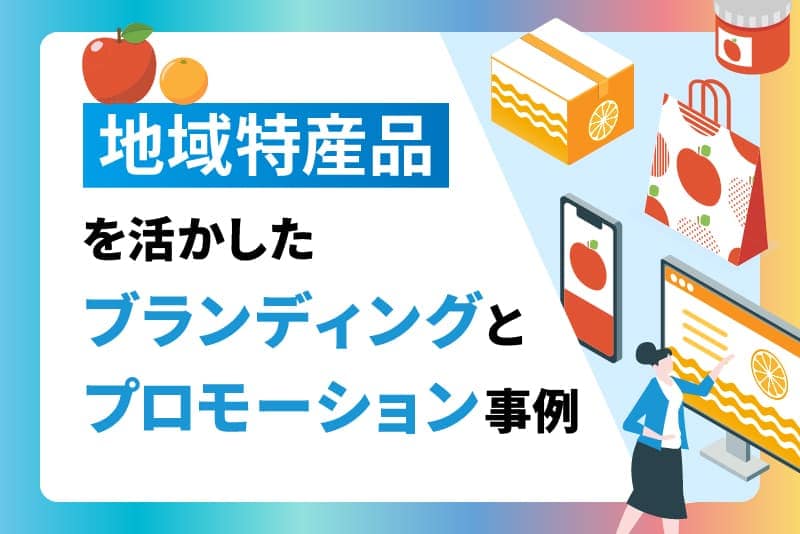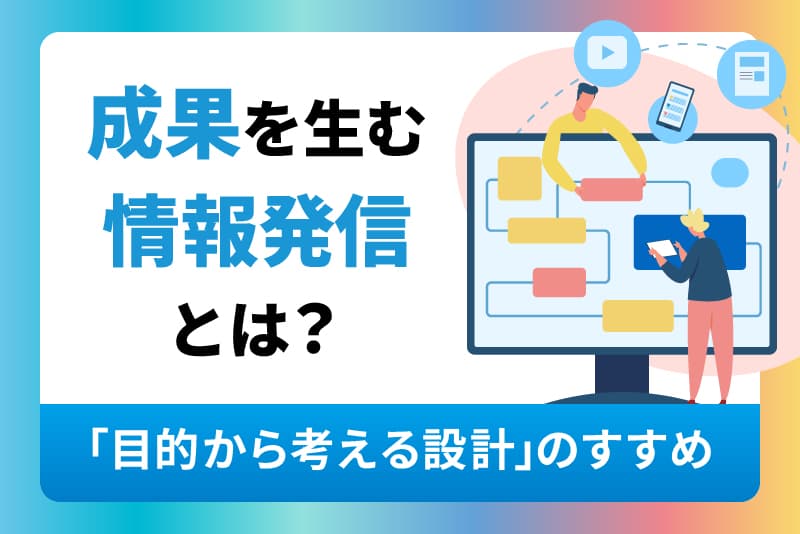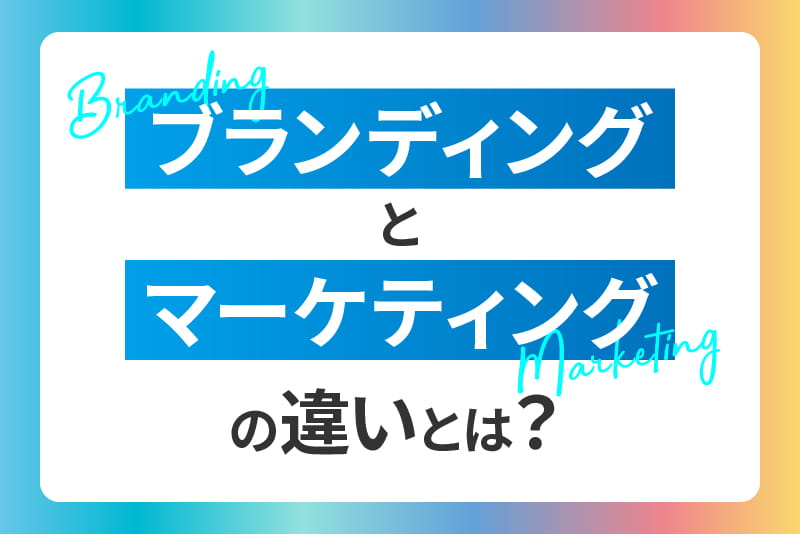
ブランディングとマーケティングの違いとは?それぞれの関係性や事例をご紹介
- WEB・デジタルマーケティング
- デザイン・ブランディング
「ブランディング」や「マーケティング」という言葉はよく耳にしますが、この二つの違いをはっきりと答えられる方は意外と少ないかもしれません。
ブランディングとマーケティングについての理解を深めることは、今後のビジネス戦略において大切なポイントです。
本記事では、ブランディングとマーケティングの違いや、2つの関係性について当社(セキ株式会社)の事例や、ディレクターのこだわりも交えながら詳しく解説していきます。ブランディングの強化やリブランディングを検討されている方、または、新たにデジタルマーケティングの導入を検討されている方は、本記事をぜひご覧ください。
目次
ブランディングとマーケティングの違いとは?
「ブランディング」というのは、企業そのもの、あるいは提供するサービス・製品の価値を明確化し、その認識を消費者に定着させる取り組みです。対して「マーケティング」は、広義では商品やサービスを効率的に販売するための戦略全般を指します。
次の表はそれぞれの違いを簡単に比較したものです。
| ブランディング | マーケティング | |
| 目的 | ブランド価値の向上 | 商品・サービスの販売促進 |
| 期間 | 長期的 | 短期〜中期的 |
| 成果指標 | ブランド認知度、顧客ロイヤリティ | 売上、アクセス数、コンバージョン率 |
| 手法例 | ビジョン構築、ロゴデザイン、ストーリー性 | 広告、SEO、SNS、プロモーション |
ブランディングが企業や商品の「印象づくり」であるのに対し、マーケティングは「売上につなげるための手法」といえます。どちらも顧客に自社の価値を届ける、という点は共通していますが、それぞれの考え方や視点は異なります。双方の相違点を知ることで、より効果的な施策につなげることができるのです。
改めて二つの違いを簡単にまとめると、以下のように区別することができます。
- ブランディング=「このブランドを選ぼう」と思ってもらうためのイメージづくり
- マーケティング=商品やサービスの魅力を効果的に伝え、売れる仕組みをつくる
今回は、この定義をもとに、それぞれの基本的な考え方や具体的な事例を交えながら、両者の関係性について詳しく解説します。
ブランディングとは?
ブランディングとは、自社製品やサービス固有の価値をつくり出し、他社と差別化するための施策です。顧客自身が自然とその価値を感じ取り、その製品を選んでもらうためにどうあるべきか、を考えるのがブランディングと考えて良いでしょう。
ブランディングを行う目的は?
ブランディングをする目的には次のようなものが挙げられます。
- 顧客ロイヤリティの向上:長期的なファンを獲得
- 競合との差別化:独自性を強調
- 価格競争からの脱却:価格以外の価値で選ばれる
ブランディングの種類は?
ブランディングの種類はいくつかあり、目的によって分類することができます。
次に挙げているのは、ブランディングの種類の一例です。
まずは、自社で行うのはどのブランディングなのかを整理してみましょう。
コーポレートブランディング(企業ブランディング)
企業の方針や価値観を明確にし、「企業自体の価値や信頼性」を高めブランド力の向上を図る手法
プロダクトブランディング(商品ブランディング)
その商品に対して顧客がイメージする共通の価値を作り出し、競合と差別化する手法
インナーブランディング(社内ブランディング)
従業員のブランド理解を深め、一体感を醸成することで、企業価値を向上させる手法
パーソナルブランディング(個人ブランディング)
個人のスキルや価値観を明確にし、ブランドとして確立する手法
ブランディング実施のステップ
いざブランディングをしていこうという思っても、一体何から始めればいいんだろう?と悩んでしまう方もいることでしょう。
ブランディングは、一般的に次のような工程で進められます。
① 環境分析
フレームワークの活用で、自社の状況を客観的に整理します。適切なフレームワークを活用し、ブランドの目的や将来どうありたいかを明確にします。
② コンセプトとターゲットの設定
ブランド価値を届ける相手として「ペルソナ」を設定します。年齢・性別・ライフスタイル・価値観・悩みなどを細かく分析し、ブランドと相性のよいターゲット層を決めます。
③ 施策の実施
ブランドメッセージの策定やビジュアルデザインの統一、マーケティング施策を実行します。またこれらはブレずに一貫したものであることが大切です。
④ 実現
施策を継続的に実行し、ブランドの認知度と信頼性を高めることで、ブランドを市場に定着させていきます。
ブランディング実践のポイント
次に、ブランディングをする際に注意しておきたいポイントをまとめました。
・核となるメッセージを明確化する
「このブランドは何を大切にしているのか?」「どんな価値を提供するのか?」という点を明確にしましょう。シンプルで分かりやすいほどメッセージが浸透しやすくなります。
・ビジュアルに統一感を持たせる
ロゴやカラー、フォント、キャッチフレーズなど、ブランドの世界観を統一すると、認知されやすくなります。SNSやWEBサイト、広告などで使う言葉のトーンも統一すると、よりブランディングが強化されます。
・ストーリー性で共感を
ブランドの誕生背景や創業者の想いなどをストーリーとして伝えることで、共感を生みやすくなります。「誰に届けたいのか?」を具体的にイメージし、その人が共感できるストーリーや価値観を発信することが大切です。
・ブランド体験を重視する
商品やサービスの品質はもちろん、パッケージや購入後のフォロー、カスタマーサポートなど、顧客がブランドに触れるすべての場面で心地よい体験を提供することで、信頼が構築されます。
・継続的なコミュニケーション機会をつくる
一度買って終わりではなく、「また選んでもらう」ための施策が大切です。SNSでの交流、メールマガジンの配信、リアルイベントの開催など、顧客とつながり続ける仕組みを作りましょう。
ブランディングによって得られるメリットは?
ブランドへの信頼は、継続的なロイヤリティ顧客、つまり長くブランドを愛用してくれるファン総獲得へとつながり、他社との競争優位性を確立することができます。また、マーケティング施策の効果をより効果的に発揮できる要素にもなります。
【セキ事例①】多岐に活躍するグローバル企業グループのブランディング
ここで、当社が実際に行ったブランディング事例をご紹介します。
◆株式会社ダイキアクシス様
株式会社ダイキアクシス様は、水に関わる事業を展開し、人と地球にやさしい環境づくりに貢献するグローバル企業です。事業の急成長に伴い、「私たちは何をしている会社なのか?」を対外的により明確に伝えるため、ブランディングの強化に取り組みました。
WEBサイトのリニューアルでは、「未来への約束」をコンセプトに、企業のイメージとグループ全体のビジョンを統一的に表現。視覚的にも一貫性のあるデザインを採用しました。
さらに、社内ワークショップの開催やクライアントとの対話を通じて、自社の強みを整理し、WEBサイトのメッセージに落とし込むことで、企業イメージの明確化を図りました。
こうして生まれた独自性のあるサイトデザインは、企業パンフレットや広告にも活用され、世界中のどの事業においてもダイキアクシス様の魅力を発信できるブランディング施策となりました。

SEKIディレクターのこだわり
ブランディング関連のお仕事は、ネーミングを含めたロゴデザインやWEBサイトのリニューアル、パンフレットの制作、新ブランドの立ち上げにおけるコンセプトワークなど、入口も範囲も様々です。 自社・競合分析などをさせていただくのはもちろんですが、加えて、誰に知られ愛されてほしいブランドなのかを重要視し、そのステークホルダーになる方々に会ったりお話を聞いたりする機会も設けさせていただいています。
ブランディングも、最終的には企業活動になんらかの成果をもたらすものであり、考えられる影響範囲や時間軸を可能な限りイメージして、ロジカルに構成していくプロセスも大切にしています。自分たちの手を離れたあと、思いがけない場所でふとそのブランドに再会した時、嬉しさを感じますね。
さて、ブランディングについて理解を深めたところで、次はマーケティングについて考えてみましょう。
マーケティングとは?
マーケティングは顧客のニーズを把握し、商品やサービスの開発・販売促進を通して企業利益を生み出す仕組みづくりを行います。
ただ単に「売る」というだけでなく、「誰に」「何を」「どのように届けるか」 を戦略的に考え、市場での競争力を高める役割を担います。
マーケティングを行う目的は?
マーケティングの目的には次のようなものが挙げられます。
- 売上の最大化:効率的な販促活動
- 市場拡大:新規顧客の獲得
- 顧客満足度の向上:ニーズに合った商品提供
マーケティングの種類は?
目的やターゲットに応じて最適な手法を選びましょう。
マーケティングの種類をピックアップしてご紹介します。
デジタルマーケティング
SNS、Web広告、SEOなどインターネットを活用したマーケティング手法
オフラインマーケティング
CM、展示会、DMなど、リアルな場面での接触を重視した手法
ダイレクトマーケティング
メルマガや自社ECサイトを活用し、企業が直接顧客とコミュニケーションを取る手法
他にもマーケティングの手法は様々です。ブランディングもマーケティング施策の中の一つであり、両者を組み合わせることでより強力な戦略を構築できます。
マーケティング実施のステップ
次にマーケティングの一般的な手順をご紹介します。
① リサーチ
市場や競合の動向、ターゲットのニーズを調査します。
主な手法として、アンケート調査・インタビュー・SNS分析・アクセス解析 などがあります。
これにより、現在の市場環境や顧客の課題を明確にし、戦略設計の基礎を作ります。
② 戦略設計
状況に合わせた最適なフレームワークを使い市場の分析を行います。
また、ターゲットの設定、ポジショニング、KPI(重要業績指標)の決定も行います。
③ 実施
大きく分けて二つあります。
「製品・サービス企画」
市場のニーズに合わせた商品開発・サービスの設計を行います。
「プロモーション活動」
広告、SNS、コンテンツマーケティング、PRなどを活用し、ターゲットへアプローチします。
④ 評価・改善
施策ごとにKPIを設定し、効果測定を行いながら改善を繰り返します。
例えば、広告のクリック率・コンバージョン率・売上の変化 などを分析し、次の施策に活かします。
マーケティング実践のポイント
次に、マーケティングをする際に注意しておきたいポイントをまとめました。
・ターゲットを明確にする
誰に届けるのかを明確にし、ペルソナ(理想の顧客像)を設定することで、効果的なマーケティングが可能になります。
・顧客ニーズを徹底リサーチ
アンケート、SNSの口コミ、競合分析、検索トレンド調査などを活用し、実際のニーズに基づいた施策を立案します。
・適切なマーケティング手法を選択
ターゲットが利用するメディアやチャネルを見極め、最適な方法(SNS・ブログ・メール・広告など)でアプローチします。
・ブランドの強みを活かしたメッセージを設計
競合と比較したときの「独自の価値(USP)」を明確にし、ターゲットに響くメッセージを作ります。機能的な価値だけでなく、ブランドのストーリーや世界観、共感を生む要素も大切です。
・データの活用・分析
「勘や感覚」ではなく、データを基に施策を最適化します。
広告の効果測定、アクセス解析、売上データなどを活用し、改善点を見つけます。
・顧客との継続した接点をもつ
新規獲得だけでなく、リピーターを増やすことが大切です。メルマガやLINEなどでフォローし、定期的に関係を深めましょう。ロイヤル顧客を育て、口コミや紹介を促したりします。
また、会員プログラムや特典、限定コンテンツの提供し、顧客のロイヤリティを高めることも有効です。
マーケティングによって得られるメリットは?
マーケティングを行う最も大きなメリットは市場ニーズを把握することで効率的な販売戦略を実行できることです。ターゲットに適した手法を選ぶことで、商品の訴求力が高まり、見込み顧客の獲得につながります。 また、一貫性のあるマーケティング活動はブランド価値の向上にも寄与し、競争優位性を確立する要素となります。
【セキ事例②】マーケティング調査から「イミ消費」に着目
続いて、当社が実際に行ったブランディング事例をご紹介します。
◆一般社団法人キタ・マネジメント様
かつて養蚕業が栄えていた愛媛県大洲市。歴史あるこの地でまちづくりを行う観光地域づくり法人の一般社団法人キタ・マネジメント様とともにシルク製品の開発からマーケティングまでを一貫して行いました。
購買ターゲットのペルソナ設計や分析からターゲットの購買行動の「イミ消費」に注目し、「大洲産シルク」の希少性やストーリー性をコンセプトに設定(イミ消費とは、物質的な価値・体験のみならず社会貢献性・自己表現・成長性といった意味を重視した消費のこと)。その開発過程を地域マスメディアやコミュニティへ発信したことが、「大洲産シルク」への関心・期待感の醸成へとつながりました。
詳しくは下記よりご覧ください!

SEKIディレクターのこだわり
マーケティングのご相談をいただくきっかけは、新ブランドや新商品の立ち上げ、WEBサイトのリニューアル、WEBプロモーションの導入、インサイドセールスの強化など、多岐にわたります。ブランディング支援と並行して、マーケティング施策をサポートするケースも少なくありません。
当社では、ビッグデータ解析ツールやお客様の保有データ、サイトの解析データを活用し、パートナー企業とも連携しながら、最適な戦略を立案ができるよう心がけています。
マーケティングは常に変化するため、施策の検証や成果確認を繰り返しながら、改善を重ねることが重要です。そのため、ご支援は短期間ではなく、1年以上にわたり伴走しながら継続的にサポートさせていただくことがほとんどです。
どっちが先?関係性から考えるブランディングとマーケティング
ブランディングとマーケティング、どちらが先かという議論はありますが、実際には互いに影響し合いながら進行することが理想的です。
確固としたブランドのイメージを立てることによって、その後のマーケティング活動において一貫性のあるメッセージを発信できます。
この一貫性こそが消費者との深いつながりを生み出し、新規顧客獲得や売上向上につながります。
一方で、市場調査などのマーケティング活動から得られるデータは、ブランド戦略の見直しや改善にも活用されます。結果として、ブランディング施策にも相乗的に効果をもたらす、長期的なビジネス成長への道筋となります。
このようにブランディングとマーケティングはお互いを補い合う関係にあり、それぞれ異なる視点から企業価値を高めることができます。
ブランディングとマーケティングは成果検証の違いに注意!
相互補完の関係にあるブランディングとマーケティングですが、それぞれの成果検証の違いには注意が必要です。
まず、ブランディングについては長期的な視点で進めることが大切です。ブランド認知度向上には時間とプロセスが必要であり、一貫したメッセージや価値提供によって徐々に市場での存在感を高めていきます。
一方マーケティングは短期的な定量データで効果を測定します。
例えば【認知度の向上】を目標とした場合はWEBサイトのPV数やSNSフォロワー数、【集客やリード獲得】であればコンバージョン率、メルマガの登録者数などで成果検証を行っていきます。
ブランディングは長期的視点、マーケティングは短期的な視点で成果検証を行うということを覚えておきましょう。
ブランディングとマーケティングの違いとは?それぞれの関係性や事例をご紹介【まとめ】
ブランディングとマーケティングは、どちらも企業や商品の価値を高めるために欠かせない要素です。ブランディングは「このブランドを選びたい」と思わせるためのイメージづくりであり、企業の理念や価値観を明確にし、顧客に浸透させることを目的としています。一方、マーケティングは「商品やサービスをどう売るか」を考え、ターゲットに適切な方法で価値を届ける仕組みを作ることが重要です。
この二つは密接に関係しており、ブランディングが確立されていれば、マーケティング施策の効果も高まります。
企業が長期的に成長するためには、ブランディングとマーケティングの施策は一方に偏るのではなく、どちらも適切に実施し、一貫したメッセージを発信することが不可欠です。自社の強みを活かし、最適な戦略を立てることで、より多くの顧客に価値を届けることができるでしょう。
いかがでしたか?今回は、ブランディングとマーケティングの違いや関係性 について解説しました。大きな枠で考えればブランディングはマーケティング施策のひとつともいえますが、それぞれの役割を正しく理解し、戦略的に組み合わせることで、より効果的なブランド価値の向上が可能です。
当社では、マーケティング・ブランディングの豊富な実績 をもとに、企業の成長をサポートしています。自社のマーケティング戦略やブランディング強化をお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。